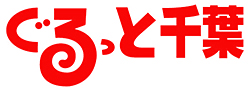【BOSO Rhum Agricole blanc Soleil -太陽-】自社農園にて自然農法で育てられたサトウキビを100%使ったアグリコールラムは数量限定販売。IWSC(international wine&spirits competition)で日本のラムとして初の金賞を受賞したほか、ラム酒の製造を手掛ける青木大成さんは、フランスのGault & Millau誌でラムに携わる世界の15人に選定された。700ml/Alc.59%/7700円。モラセスを原料にしたトラディショナルラムは「BOSO Rhum blanc Fleur -花-」と「BOSO Rhum blanc Fleur -花- Contient de la melasse」の2種を用意。各700ml/Alc.40%/3960円
栽培から蒸留まで。
房総のテロワールを宿すラム酒の味わい
海の印象が強い千倉だが、こんなにも秘境めいた山道があるのかと唸る。手に汗握りながら車のハンドルを操作し、ようやく辿り着くと、立派な長屋門がお出迎え。背後には築百五十年ほどの母屋が佇み、隣には工房が。その工房がラム酒の蒸留所「房総大井倉蒸溜所」であった。 「原料となるサトウキビは、海辺の地区で栽培しています」と、驚くべき話とともに案内してくれたのは、ラム酒の製造を手掛ける「ペナシュール房総」の青木大成さんだ。沖縄のように越冬はできないものの、霜が降りず寒暖差があるため、糖度の高いサトウキビが収穫できるのだという。しかも南房総の環境を活かした自然栽培が行われている。この千倉産サトウキビで作られたラム酒は〝アグリコールラム〟に分類される。 市場に出回るラム酒の大部分は、モラセス(※)を使った〝トラディショナルラム〟と呼ばれるもの。一方、アグリコールラムは「サトウキビを搾ったジュースをそのまま発酵させて蒸留します」と青木さん。その搾り汁は傷みやすいのですぐさま加工しないといけない。栽培地の収穫期でないと作れないのがアグリコールラムだ。とはいえ、どちらの味が良い悪いではなく、それはあくまで好み。ペナシュール房総では「すっきりとした甘みを感じられるラム酒」として、国産モラセスを原料にしたラム酒も製造している。だが、房総のテロワールを宿しているのはいうまでもなくアグリコールラムで、フラッグシップに位置付けられている。青木さんが「オイリーな味わい」と表現するように、ねっとりと甘やかな香りが立ち上り、ボディのある風味が特徴的。それでいて意外なほどにクセがなく、ロックやストレートでも非常に満足感が得られるおいしさであった。 それにしてもなぜ、房総でラム酒なのか。その答えは千倉出身の青木さんが教えてくれた。「戦後から昭和50年代にかけて、千倉では自宅の庭などでサトウキビを栽培していたんです」。そう、千倉は元々サトウキビを栽培していた土地柄だったのだ。そうした背景がある中、親戚が住んでいたこの古民家が空き家になったタイミングで、故郷で蒸留所を設立する決意を固めた。 「今後は魚介とのペアリング、ラムを使ったスイーツなどを提案して、地元食材に着目するきっかけづくりをしたい」と意気込む青木さん。活動のさらなる展開に期待したい。
※糖蜜のこと。砂糖の製造過程でサトウキビジュースは砂糖の結晶と糖蜜に分離される
(取材・文:沼尻亙司、撮影:織本知之)

1.右手に見えるのは自社考案のオリジナル単式蒸留器。なんと給食などで使う大鍋をカスタマイズしたもの 2.こちらは連続式としても使えるハイブリッド型銅製蒸留器 3.蒸留後の抽出液は最初と終盤に不要な部分が出るため、どの位まで中央部の抽出液を取るかが腕の見せ所 4.蔵は熟成庫に活用。今後は房総のマテバシイを熟成樽にする予定だ 5.瓶詰め作業 6.母屋は宿泊施設として生まれ変わった 7.長屋門は試飲ルームにする計画。整備が進む
住所 〒295-0012 南房総市千倉町南朝夷1019
電話番号 0470-29-3953
営業時間 ※蒸留所で直売は行っておりません。事前予約による試飲見学ツアーの申込はwebサイトを参照
WEB https://rhumboso.com
販売・お取り寄せ 【販売箇所】ちくらつなぐホテル内直営SHOPなどで販売 【お取り寄せ】webショップで受付
※2024年1月号に掲載
※掲載されている情報や写真については最新の情報とは限りません。必ず事前に公式サイト等でご確認の上、ご利用ください